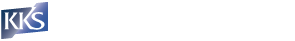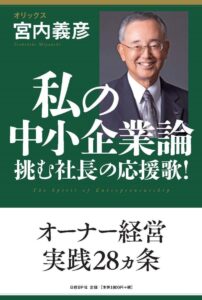№158-R6.8月号 金利ある世界
超低金利時代
日銀は7月31日の金融政策決定会合で政策金利を現行の0~0.1%から0.25%へ引き上げることを決定しました。3月にマイナス金利解除、イールドカーブ・コントロール(長短金利操作)の撤廃などを実施し、金利上昇への布石を打っていましたので、今回の引上げにより大手銀行各社が短期プライムレート(以下、短プラ)の変更を通じて住宅ローンの金利や企業の借入金利が上がるほか、預金金利も上昇することになります。
政策金利は実に15年7カ月ぶりの水準に、短プラは2007年3月以来の引上げになる見込みです。既にメガバンク3行は短プラを年1.475%から1.625%に、普通預金の金利を年0.02%から0.10%に上げることを発表しており、他の大手銀行や地銀、信金も追随することが予想されます。いよいよ「金利ある世界」の始まりです。
日本では日銀がゼロ金利政策を決定した1999年以来、短期政策金利は極めて低い水準で推移してきました。特に2014年12月の第2次安倍政権発足後はアベノミクスの第1の矢である「大胆な金融政策」で企業や家計で金利は負担というレベルではなくなっています。
当時の黒田日銀総裁が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」として当座預金の一部にマイナス金利を適用し、金融機関が企業への貸し出しや投資に資金を回すよう促すことで経済の活性化とデフレ脱却を達成する目的で今日までマイナス金利政策が続いてきました。経緯を振り返ると20代~30代の世代は「超低金利」が当然で今日を迎えていることになります。
金利引き上げ根拠への疑問
今回の政策金利引き上げには、日銀が2026年度まで賃金の上昇に伴う2%程度の物価上昇率が続くシナリオを描いていることが背景にありますが、国民の多くはその分析と感度に疑問を抱いているのではないでしょうか。統計を見る限り、物価上昇の根拠となる「消費者物価指数(生鮮品除く総合)」は2022年4月から前年比2%超を継続しています。
しかし、この物価上昇は、本来の需要牽引型の物価上昇ではなく、輸入コストの上昇圧力による止むを得ない物価上昇です。米国のFRBが景気引き締めのために金融政策として政策金利を引き上げている(5%程度)のとは意味が違います。
また、「賃金の上昇」についても、「現金給与総額」の前年比は1%台の上昇が多く、同時期の比較で前述の物価上昇率を上回らない「実質賃金マイナス」の状態です。そのため、家計の負担が増えている状況でさらに金利上昇が加われば、住宅や自家用車のローンでの購入に躊躇してしまうことが考えられ、実態経済にとって逆効果のような気がします。
金利の意味と影響
政策金利とは、短期金融市場の「無担保コール翌日物金利(オーバーナイト物)」を指します。今回「政策金利を0.25%に引き上げる」ということは、市中銀行との間で主に国債を売買することで毎日0.25%になるよう金利をコントロールするということです。
政策金利は短プラ(金融機関が優良企業向けの1年未満の短期貸出に適用する最優遇金利)に影響しますので、大手銀行からこの決定に反応します。短プラが引き上げられた場合、変動型住宅ローンの金利にも直結するのですが、住宅ローンには金融機関で「5年ルール」や「125%ルール」を設定している場合が多く、仮に金利が上昇したとしてもその都度毎月の返済額が増えるわけではありません。
企業向け融資の場合は、短プラよりも現在では東京銀行間取引金利(TIBOR)の採用が主流になっている印象です。融資金利はこのTIBORにスプレッド(金融機関の利ざや)を上乗せして決まります。金融機関は「市場金利(TIBOR)が上がったので、○月から金利が△%上がります」とう内容の「変更通知書」を送付してきますが、頻度が上がるようであれば「スプレッドの部分で何とかなりませんか?」と交渉してみるのもよいかもしれません。
超低金利が当たり前で資金繰りを融資に依存しがちな体質になっているのであれば、今後金利負担は大きく伸し掛かることになります。そろそろ「金利ある世界」への準備が必要です。
<複製・転写等禁止>