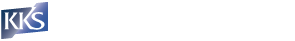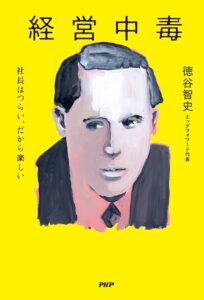№168-R7.6月号 令和のコメ騒動
騒動の発端と現状
コメの価格の高騰に関する報道が長期間続いています。今月上旬に発表された2025年上期の日経MJヒット商品番付で、「米(コメ)フレーション」という言葉が東の横綱(実質1位)に選ばれるほどの注目度です。
前年対比3%台のインフレ率で実質賃金が上がらない状況に加え、金利の上昇が追い打ちをかけるタイミングですので国民の関心が高まるのも無理はありません。
2023〜2024年にかけて猛暑や台風の影響による収穫量の減少、インバウンド消費の増加、減反政策の影響による作付面積の縮小などにより、コメの供給量が不足したことが今回の価格高騰の主な要因と考えられています。
加えて、江藤前農林水産大臣の不適切発言に始まり、自民党農水族と関連団体との癒着、出来レースのような政府備蓄米の入札での放出など、政府の対応の悪さがコメ騒動に拍車をかけてしまった印象です。
現時点では、石破首相が小泉農林水産大臣に指示し、大手小売各社に対して随意契約で古古米を中心とした備蓄米を放出し、概ね5㎏2,000円程度で販売が開始されています。
小泉大臣は、備蓄米を2,000円で売れるように無制限に放出するとも述べていますが、需要と供給で決まる市場価格を長期間コントロールし続けることは難しいのではないでしょうか。
コメ不足以前
コメ不足の要因の一つに、政府が誘導してきた減反政策があります。背景には日本人のコメの消費額(2人以上世帯)が年々減少しており、2012年頃からパンの消費額が逆転し、増え続けている現状もあるようです。
周知のように、日本はコメの食料需給率100%の維持と国内農家の保護を目的に、国家貿易で輸入する「ミニマムアクセス米」以外の輸入には1㎏あたり341円の関税を課してきました。 過去には、農林水産省が世界貿易機関(WTO)の貿易自由化の交渉で、コメの関税について当時のコメの価格に基づき税率に換算すれば778%になると指摘されたこともあります。
一方で、日本では1970年代以降、主食用のコメ余りが問題となり、コメの作付面積を制限する減反政策が導入され、コメから飼料用米や麦、大豆などに転作した農家に補助金を給付することで、コメの生産量を減らして、価格を市場で決まる水準より高く維持してきたのです。実際に、コメ余りの兆候は最近まで続いており、コロナ禍での外食需要の落ち込みもそれに拍車をかけました。
商売においても、円安で値上がりした小麦粉の代わりに米粉のパンを増やすなど、菓子や味噌、焼酎などの加工品にも積極的に使用するようになっていたと思います。しかし、長年のコメ余りが、一転、コメ不足になってしまい、特に、コロナ禍明けでようやく需要が回復傾向にあった外食産業などは戸惑いを隠せません。
適正価格の行方
全国約2100社の農業法人などが加入する「日本農業法人協会」の齋藤会長は、コメの適正価格について、「私たち農家としてできれば3,000円ですね。3,500円を要求すると輸入がばんばん入ってきます」と述べ、輸入米の流通をけん制しました。
具体的に、農家は3,000円程度が適正であり、競争優位が保てる価格と判断しているようです。大半の日本人が日常において外国産のコメを食べる機会はないでしょうし、1993年の「平成のコメ騒動」の際のタイ米(インディカ米)の印象で、敬遠しがちな方々も少なくないのではないでしょうか。
最近では、国産米とタイ米の中間の粒の大きさで、粘り気が少なく、パラパラとした軽い食感が特徴の「カルローズ米(ジャポニカ米)」(加州米)が、イオンやコストコで、5㎏3,000円程で販売され、評価も高いようです。
国産米に関しては、高い関税をかけて農家を守り続けることが正解か否かは難しい判断になります。JAの流通経路が複雑なことやJAバンクの預金量、全農の事業利益が想定外に多額であることも事実とはいえ、長期間コメの価格を安価に維持してきたことに間違いありません。今後、一般的に流通するコメがどのような種類でどのような価格に収まるのか、今年の収穫が決まり、来年の作付けが始まる1年後が興味深いです。
<複製・転写等禁止>