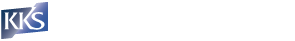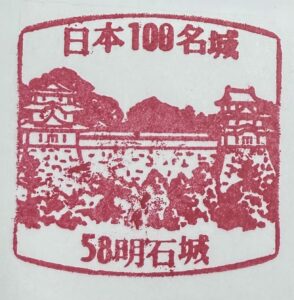№165-R7.3月号 先細るGDP
後退する日本の順位
これまでも本稿で名目GDP(国内総生産)が日本全体の付加価値の合計であり、GDPが増えない限り国民の給料は上がらないことを述べてきました。特に大きな話題になっている印象はありませんが、2023年に日本はドイツに名目GDPで抜かれ世界第4位に、今年はインドにも抜かれて世界第5位に後退する見通しです。
中国、インドは人口で圧倒的に日本を上回っていますので、総生産が高くなることは止むを得ないとしても、人口が日本の7割以下のドイツに抜かれることは少々看過できない事実ではないでしょうか。2023年時点の名目GDPは具体的に日本が4兆2106億ドルに対し、ドイツは4兆4561億ドルですが、生産性の優劣というより物価高や円安の影響が要因と考えられています。
また、毎年IMFが発表している「一人当たりGDP」は、2024年に台湾にも抜かれ、世界39位にまで転落してしまいました。個人的な見解ではありますが、日本の商品・サービスは品質や性能、安全性などのレベルが高い割に価格が安いと感じています。
言い換えれば、世界基準ではもっと高く売れるモノが長年のデフレマインド定着で適正な価格で取引されなくなっているのです。実際に訪日外国人の感想では、宿泊施設でのおもてなしや鉄道サービス、飲食店での提供物などは割安感を超えて衝撃価格に近いと答えています。
デジタル経済の反映
来月より国連が国際算出基準である国民経済計算を改定するのを踏まえ、電子商取引(EC)での購入履歴のデータベース整備などが設備投資として新たにGDPに反映されるようになります。試算では、新基準を導入すれば日本の名目GDPは1~2%強押し上げられ、2024年7~9月期に当てはめると年14兆円程になるそうです。
具体的にはECの購入履歴やPOS(販売時点情報管理)データ、スマートフォンの位置情報や健康、気象情報などが含まれ、統計上も今や生活や事業に直結しているデジタル経済の実態が把握しやすくなります。
新基準導入による押上げ効果は、オランダ、オーストラリアに次ぐ第3位とのことで、実際にGDPに反映され、為替が少し円高に振れれば再び名目GDPでドイツを肉薄する可能性も期待できそうです。
一方で、IMDという機関が毎年発表している「世界デジタル競争力ランキング」の最新(2023年)ランキングでは、日本は32位と過去最低を記録し、残念ながら世界ではデジタル後進国という評価が続いています。今回の新基準採用で一時的に名目GDPは増えますが、今後数字を押し上げていく分野として期待できるかとなると現状では難しいでしょう。
小手先の調整
名目GDPだけを長年追い続けてていると、日本はこの30年間で600兆円台まで成長してきたかのような安心感を覚えます。前述の通り、GDPの算出基準は変わることがあり、今回デジタル経済による付加価値が追加されるように、2016年の安倍政権時にも企業の研究開発費がGDPに算入されたことなどで2015年度の名目GDPは、改定前の500兆6千億円から532兆2千億円と30兆円超も増加しました。
現在の数字だけ見ると安倍政権が名目GDPを大きく押し上げ、今では600兆円規模にまで経済成長したと捉えがちですが、実態は基準が変わり新たな項目が追加されただけです。さらに、冒頭にお伝えした他国との比較では通常ドル換算での数値になりますが、日本の名目GDPはコロナ前の2019年から下がり続けています(2019年:5兆1180億ドル→2024年:4兆700億ドル)。
円安の影響も多大にありますが、為替も相場であり国力です。政府は公的統計の中核で、現金給与総額に影響を与える名目GDPを良く見せようとする傾向がありますが、経営者は日本経済の現状を冷静に正確に把握する必要があります。企業に置き換えると、営業外利益の営業収入への算入や在庫の評価方法を変えるなど小手先の調整で粗利益(≒名目GDP)を大きく見せることでは、実額で支払う給料を上げることはできないということと同じです。
<複製・転写等禁止>