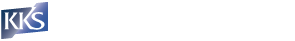№166-R7.4月号 リードタイムの短縮
リードタイムに注目
人材不足が深刻化する昨今、企業経営においても「生産性の向上」という言葉が何かと問われるようになってきています。物価や人件費の高騰に対して、粗利益をどのようにして増やすかは、販売単価の引上げ(値上げ)ばかりに頼るわけにはいかないのが実情です。そこで、今回は企業努力で改善が可能なリードタイムに注目してみます。
リードタイムという言葉自体は、製造業で「生産リードタイム」のような使われ方をされるのが一般的で、この場合、製造着手から完了までに要する時間です。この時間が短くなるほど、製品の生産量が増えるため、生産効率が高まり、売上増につながります。
「生産リードタイム」は製造業に限られた用語になりますが、「納品リードタイム」や「営業リードタイム」、「配送リードタイム」、「開発リードタイム」など様々な業種・業態でリードタイムは存在し、独自に定義づけすることも可能です。
事業活動をしていれば、何らかの商品やサービスを提供していることが前提となりますので、「納品リードタイム」であれば、受注から納品までの過程で何らかの改善・見直しの余地があるかもしれません。
売上高を構成する要素は、「販売単価」と「数量」が基本です。そのうち、リードタイムを短縮することは「数量」を増やすことになり、「生産性向上」の一翼を担う改善活動となります。
リードタイムの長期化
気付かないうちにリードタイムは長期化しています。人手不足、高齢化等による意思決定や作業の遅れ、機械装置の老朽化、原材料等の納期の遅延、効率化を考慮しない作業レイアウト、アウトソーシングの未活用など、長期化の要因は時間をかけて複雑に影響しているのです。
リードタイムの長期化は、販売数量の減少に直結するだけでなく、売上遅延、コストの増加、キャッシュフローの悪化を招き、経営体力を弱体化させます。この現象に気付いている経営者も、やむを得ず放置している現状が少なからずあることも事実です。
例えば、従業員に対して作業の生産性を高める指示が出しにくい、新しい機械装置等の導入やIT化を推進するためのコストが捻出できないなど、放置の理由を多くの現場で耳にします。
経営者は、粗利益の減少によるキャッシュフローの改善を取引先ばかりに求め、意外にも自社でコントロールできるはずの効率化は軽視しがちです。
値上げや支出削減には限界があり、ニッチトップのような存在でない限り、取引先離れが進行してしまうことになりかねません。ルーティン業務ばかりを日々淡々とこなしていると、着実にリードタイムは長期化します。
定期的に業務の効率化や無駄の削減を意識する機会をつくることで、負のサイクルへの突入を未然に防ぐことが重要です。
具体的な改善策
前述の通り、リードタイムは自社の企業努力で改善できる売上増加への取り組みです。中小企業では、まず現状の「トータルリードタイム」を把握し、細分化することで現場ごとの短縮目標を掲げるのが効果的と考えます。
では、具体的どのようなアプローチが必要か? ですが、まずは「プロセスの見直し・標準化」が必要です。
無駄な手順の削減や業務フローの最適化を追求することで、標準化が可能となり作業時間を短縮できます。従来の商慣行に依存してきた企業は「ITツールの活用」へのチャレンジも不可欠です。ERPや生産管理システムを導入し、情報共有や進捗管理を効率化することで業務の遅延が防げます。
また、製品や商品を扱う業種では「在庫管理の適正化」を図ることで発注リードタイムが短縮し、必要な資材の迅速な確保につながります。中小企業においては、特にスピードを意識しなければなりません。組織が小さいという利点を活かし、「社内コミュニケーションの強化」を進めることで、部門間の情報伝達を円滑にし、意思決定のスピードが上がり、無駄な待機時間を削減できます。
リードタイムの悪化は、自覚なく進行し、徐々に企業体力を奪う悪質な病のような現象です。粗利益を確保する手段として、つい即効性が高い対外的な価格交渉に目を向けがちですが、リードタイムを改善することで内部が活性化すれば、いつの時代も価格対応力の強い商品やサービスが提供できるはずです。
<複製・転写等禁止>