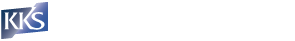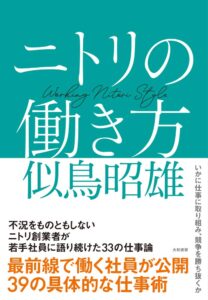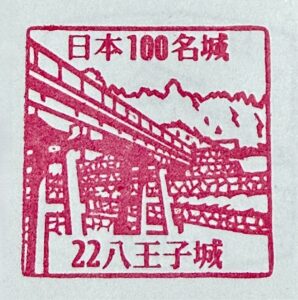№169-R7.7月号 内製化と外注
労働力不足の深刻化
労働力の確保に関する問題が一層深刻になってきています。以前から中小企業の特に製造業や宿泊・飲食業などでは悩ましい問題でしたが、外国人労働者の積極的な採用や少人数態勢による作業の工夫・改善で何とか乗り切ってきました。
統計的にも、日本の生産年齢人口(15歳~64歳)は、1995年の約8,726万人(総人口の約69.5%)をピークに減少傾向にあり、2023年10月時点では約7,395万人(約59.5%)、その後、さらに減少が続き、2030年には約6,857万人(約57.7%)になると予想されています。
ただ、健康寿命の観点では、日本は平均寿命とともに世界一(2024年2月時点)ですので、65歳以上でも現場では数多くの方々が活躍されており、特に中小企業では貴重な労働力です。このような環境下において、人件費の高騰、労働時間の減少等の条件が重荷となり、採用難は依然として続いてます。
中小企業では、内製を重視して利益や資金を確保することを原則にしてきましたが、労働力の確保が困難になってきている現状では、「外注」という選択肢を効果的に採用しなければなりません。「外注」は、文字通り外部に製造工程の一部を依頼することから人材派遣会社を介して労働力を調達するケースまで内容は多岐にわたります。便利な反面、当然ながらコスト負担は高めです。
意思決定の判断基準
一般的な外注案件の意思決定は、製造業では加工の一部依頼、繁忙期やキャパオーバーの際の受注の丸投げなど、経営者が現場の状況に委ねていることが多いようです。人手不足が深刻化する中、受注増の機会損失をしないためにも、社内で「外注」を決定する判断基準を明確にしておくと良いでしょう。
「内製化」か「外注」かの判断基準としては、例えば、①コア業務か否か、②専門性や競争力が高いか否か、③リソースとコスト、④早期・柔軟性のある対応が可能か否か、⑤信頼できる外注先か否かなどが考えられます。
①のコア業務は当然、内製化を優先させる方が効率的ですし、逆にノンコア業務は多くのロスを生み出す可能性が高くなります。 ②の技術力が優れてる場合や、競争力が高い業務は内製化すべきです。 ③は自社のリソース(経営資源)を把握し、コストを検討した上で判断する必要があります。
また、④のスピードや変化への対応が柔軟かどうかも見極めの重要なポイントです。スピードは回転率を高めますし、受注先の注文や設計などの変更に柔軟に対応できれば受注増にもつながります。最後に⑤は、やはり、取引する外注先が信頼できることが大切です。
外注先は、自社商品の一部を担ってもらう大切なパートナーでもあります。自社に対して長期にわたり優先的に関わってもらえるような信頼関係を築くことが重要です。
外注先との共存共栄
意思決定の判断基準が固まると、ある程度パターンが決まり、数字として結果にも表れてきます。判断基準を社長の勘だけに頼り続けると、受注が減少した際にコア業務ではない業務を内製化しようとして、時間やコストに大きくロスが生じたり、重要性のない業務まで受注して、自社で対応できずに外注に依頼して原価割れしたりといった事態を招くことになります。
結論としては、中小企業はコア業務の内製化を基本にしながら、信頼できる外注先を確保して併用することです。適切な判断基準のもとで会社の規模や成長ステージに応じて、その比率を調整する精度が高まれば、競争力や生産性は確実に高まります。一方で、外注先においても後継者不在や社員の高齢化、コスト増等での経営難が深刻化しており、廃業や倒産、規模の縮小も増加している状況です。
外注依存度を上げてしまうと、主要外注先がやむを得ず廃業等を選択した場合に自社も多大な損失を被ることになります。専属受注先への対策は入念でも、実質専属の外注先へは無防備な場合が多いです。
企業の存続という立場からも内製化と外注の意思決定は益々重要になっています。独自の判断基準を持ちつつ、取引先との共存共栄を意識することで、サプライチェーン全体としても生産性を高めていくことが重要です。
<複製・転写等禁止>