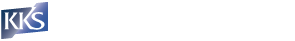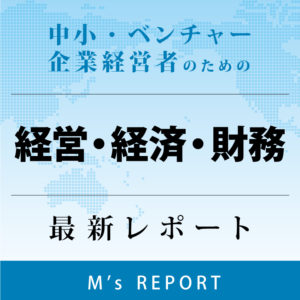H23.10月号 増税が与える影響
臨時増税の内容
政府・民主党による東日本大震災の復興財源に充てる臨時 増税案が大筋で固まりました。増税規模は11.2兆円、さらに政 府が保有するJT株やエネルギー関連株の売却で2兆円を捻 出できれば、9.2兆円になる見込みです。
増税案の主な内容は、
⓵法人税:2012年4月開始事業年度から、11年度税制改正に盛り込まれた5%の恒久減税を実施したうえで減税幅の範囲で3年間増税
⓶所得税:2013年1月から10年間、4%の定率増
⓷税個人住民税:2014年6月から5年間、均等割を500円増額
⓸たばこ税:2012年10月から10年間、1本当り2円引き上げ
となっています。相続税に関しては、臨時増税の期間中に 死亡した人の遺産だけ増税対象となるのは不公平との考えから今回見送られました。「一時的な支出は一時的な歳入で確 保する」という観点では、可能な限り税外収入を活用して税負 担を軽減してもらいたいものです。
その他の増税と企業負担の増加
臨時増税の内、直接企業へ影響を及ぼすのは、⓵の法人税です。当初より予定されていた5%の減税範囲内で増税分が 相殺されることになりそうですので、実質増税とはなりませんが、円高や貿易自由化の遅れ、電力不足(かつ割高な電気料金)など企業を取り巻く環境が大変厳しい状況にあることを考えると、3年間は限界をはるかに超えています。その間に「産業の空洞化」がさらに進行すれば、国内雇用の減少ばかりでなく 法人税収自体も大きく減少しますので、本末転倒という結果にもなりかねません。
そして、今回の臨時増税にだけ着目するとつい見失いがちですが、企業にはさらなる税負担がやってきます。菅内閣が打ち出した「社会保障と税の一体改革」の財源として、「消費税率を2010年代半ばまでに段階的に10%まで引き上げる」です。
前号でもお伝えした通り、デフレ経済が当分 続ことが予想されますので、売価への価格転嫁が見込めない状況での消費税率引き上げ分は、実質企業負担になると考えられます。さらに、企業負担の増加という意味では厚生年金保険料も2017年まで料率が毎年0.354%ずつ引き上げられることに加え、パート労働者に対しての適用範囲の拡大(「週30時間以上」から「週20時間以上」等)も検討されています(従業 員300人以下の中小企業や学生は除外)。
また、所得税の増税についても4%とはいえ10年という長期間ですので、消費税率アップとも重なって個人消費を冷え込ませることになり、間接的に企業収益を圧迫する要因となり得るでしょう。このように税負担の増加だけを取り上げてみても、企業への制度的逆風は今後も強まるばかりです。
デフレ下の増税
リスク増税の是非はさておき、デフレ経済下の増税がもたらす影響について考える時、日本は過去に同様の経験をしています。それは、消費税率が3%から5%に引き上げられた1997年です。日本経済は15年間デフレが続いているといわれていますので、当時すでにデフレに入っていたことになります。消費税率は2%上がったものの、一般会計の税収は1997年の53兆円をピークに、直近の2010年までその額を超えていません。折しもその2年前に阪神淡路大震災が発生し、補正予算で復興需要を作り、ある程度経済成長率が上がった時点での増税だったはずです。
このことを踏まえると、今回のパターンは類似しており、さらにデフレが浸透している中での増税となり、経験則上ではネガティブにならざるを得ません。本来は金融緩和効果でデフレを脱却した後の増税が望ましいのですが、財政面から考えた場合、財政赤字の伸びを軽減することも日本にとっては急務であり、歳出削減とともに税収増は確かに必要です。
ともあれ、今回の(消費税率引き上げを含めた)増税スケジュールが企業または個人負担を強いた上、15年前と同様、かえって税収減をもたらす結果にだけはならないことを期待します。
〈複製・転写等禁止〉