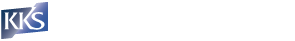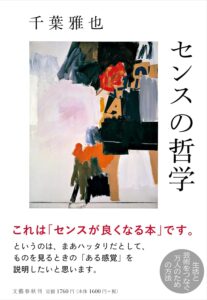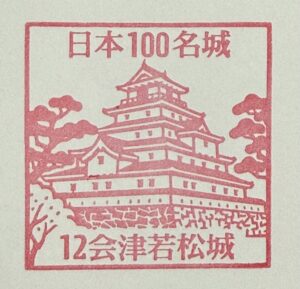№172-R7.9月号 「役員貸付金」の功罪
銀行と税務署の視点
同族会社が社長やその親族にまとまった資金を貸し付ける取引については、好業績をあげている企業ほど、あまり良い印象を持っていないのではないでしょうか。
その主な理由としては、「銀行の融資に影響する」や「税務署に目を付けられそう」といった回答が多いようです。銀行は、融資した資金が会社の事業活動に適切に使用されることを前提としています。その資金が役員個人に流れている場合、資金使途が不透明と判断され、経営に対する信頼性が低下することになります。
また、役員への貸付が増えれば、会社の資金繰りにも影響を及ぼす可能性があるため、融資審査の際には慎重な対応が取られると考えられます。たとえ、融資資金とは別に、利益から生じた余剰資金を原資として役員に貸し付けた場合であっても、銀行は決算書に「役員貸付金」が計上されているだけで、形式的に判断する傾向があるため、今後の融資に不利に働く可能性が高いといえるでしょう。
一方、税務署は別の視点からこれを見ています。税務署は、同族会社における公私混同の有無に特に目を光らせています。「役員貸付金」があると調査官には、公私混同が起きやすい会社とみなされがちです。
ただし、使途について厳しく追及されるわけではなく、契約書が作成され、適正な利息の徴収と確実な返済が実施されている場合には、特に問題視されません。
税務リスクへの備え
税務署とのトラブルを防ぐためには、前述の契約書(『金銭消費貸借契約書』)をきちんと作成し、その内容通りに実行することが重要です。
貸付けが社長の私的な流用であった場合、役員賞与として認定される可能性があり、最悪の場合、全額が損金不算入となり、法人税等の追徴課税に加え、延滞税や社長個人の所得税・住民税の追加納付という事態にもなりかねません。
また、貸付期間に応じた利息相当額も認定され、法人側の課税対象となります。実務では、交際費や消耗品費などの名目で私的支出された金額が、やむを得ず「短期貸付金」や「未収入金」に計上されている決算書も見受けられますが、残高が積み上がるほどにリスクは高まります。
利息については、所得税基本通達36-49を参考にすべきです。通達では、「使用者が役員または使用人に金銭を貸し付けた場合の利息相当額は、(中略)その年の租税特別措置法第93条第2項に定める特例基準割合に基づく利率により評価する」とされています。
直近では、この特例基準割合は年利0.9%(令和4年~)となっており、銀行からの借入残高がある場合にはその借入利率を適用することで、認定利息のリスクを回避できると考えられます。
個人投資としての活用
会社の手元資金に余裕があり、無借金経営かつ今後も銀行融資の予定がない場合、正当な『金銭消費貸借契約書』を作成して、例えば社長に5,000万円を貸し付けるという選択肢も考えられます。特例基準割合(年利0.9%)に基づく金利であれば、社長は非常に有利な条件で資金を調達することが可能です。
信用金庫のフリーローンでは一般的に年利3.0%~15.0%程度の金利が設定されており、融資限度額も高くありません。仮に、この資金を利回り10%の賃貸物件の購入に充てた場合、年45万円の利息負担で500万円の家賃収入が得られることになります。外国債券や金などへの投資によっても、利ざやを稼ぐことができ、返済の途中で退職金と相殺することも可能です。
会社から個人へ資金を移すには、通常、役員報酬や配当を通じて税金や社会保険料が発生しますが、このようなスキームであれば、その負担を抑えることができます。まれに経営者が財テクで利用する「小規模企業共済」の契約者貸付より金利面(1.5%)でも有利です。
「役員貸付金」は、銀行や税務署の目にはネガティブに映る可能性がありますが、形式(契約書の作成、利息設定)と実態(返済履行、使途の妥当性)を整えたうえで活用すれば、会社と社長双方にとって合理的な選択となるでしょう。今一度、「役員貸付金」の意義とリスクを理解し、慎重かつ戦略的に判断することが求められます。
<複製・転写等禁止>