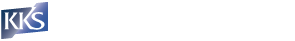№93-H31.3月号 法人生保、「売り止め」の背景
「節税保険」にメス
先般、大手生命保険会社が相次いで「節税保険」の販売を中止しました。「節税保険」とは、通常、契約者である企業が中途解約を前提に保険料を全額損金にできる商品を言います。
具体的には、業績好調の会社が利益を圧縮する目的でこの保険に加入すると、支払った保険料が全額損金になり、契約期間中は毎期の法人税等を低く抑えることができる仕組みです。その後、この保険を解約する際には、当然ながら返戻金が益金に計上されることになりますが、そのタイミングで相応の退職金を支払うことで出口の納税も回避することが可能になります。
返戻率も高いため、このスキームが経営者に大変受け、2017年4月に日本生命が販売を開始してから爆発的に売れ続けた結果、2017年度で市場規模は8000億円に達し、5年前と比較して6割も増える勢いとなりました。そのため、「節税」を過度に強調した販売が今回国税庁や金融庁に問題視され、規制がかかる運びとなったのです。
経営者の皆様も、生命保険会社とは何らかの取引があると思いますので、最近まで「今ならまだ契約できます」などといった「売り止め話法」を耳にされたのではないでしょうか? 私は何故か税理士事務所からこの手段で勧誘がありましたので、正直少し引いてしまいました。
「売り止め」の背景
2月13日、国税庁は生保41社の担当者を緊急招集し、今回の販売過熱に対して法人税基本通達を抜本的に見直す方針を示しました。
国税庁が各社に示したポイントは大きく3つで、1つは、長期平準定期や逓増定期をはじめ、これまで商品個別に決めていた損金算入割合の通達を廃止すること。もう1つは、新たな算入ルールについては解約返戻金の返戻率が50%を超える商品を対象とすること、最後に、解約返戻金のピーク時の返戻率に応じて、損金算入の割合を区分けすることです。
生保業界は国税当局に、これまでも節税商品を巡って何度か規制をかけられてきました。2008年には「逓増定期保険」、2012年には「がん保険」といずれも全額損金算入できる商品を開発し、販売を強化すると制限をかけられるといった具合です。
つまり、国税当局は常に「後出しじゃんけん」ができるわけですが、そろそろ「いたちごっこ」を解消したいという意思表示が、幅広い保険商品を対象とした通達見直しに表れている感じがします。
一方、金融庁は規制緩和の一環で、付加保険料(運営コスト)を認可外とし、企業努力で保険料が下がることでの商品普及を促しました。しかし、意図に反して「節税保険」への集中で付加保険料が膨らむ結果になってしまったため、生保各社の姿勢を強く批判しています。
保険契約の本質的な考え方
同じ商品でも切り口を変えると、生保は会社にとって必要不可欠なアイテムであることに気付きます。その切り口とは「企業防衛」です。
会社は通常、設備投資などである程度の借金を抱えていますが、社長が不慮の事故や病気で亡くなってしまった場合、突如として存続が危ぶまれる事態に陥ってしまいます。特に、小規模企業の場合は社長の影響力は絶大です。社長亡き後、後継者がいなければ、会社を清算するにしても借金の返済以外に従業員の退職金や清算費用も必要になります。内部留保が十分あれば問題ありませんが、中々そのレベルに達している会社は少ないのが現状です。その意味では有事の保障を生命保険で担保しておくことは、「企業防衛」という観点から非常に大事な考え方と言えるでしょう。
生命保険に加入する目的は、第1に企業防衛、第2に役員退職金や設備投資への備えで、保険料の全額損金算入という条件も魅力的ではありますが、本来優先順位は然程高いものではありません。即効性のある「節税」には、大抵何らかの「副作用」が伴います。とりわけ「経営」という視点においては、生命保険契約に限らず、目先の利得ではなく、本質的な部分を的確に見据えて意思決定すべきなのです。
<複製・転写等禁止>