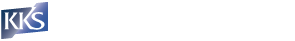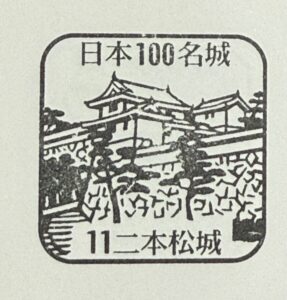№172-R7.10月号 「合理的な昇給基準の考え方」
最低賃金上昇率
経営者の皆さまから寄せられる相談の中で、最近は『従業員の昇給をどのように合理的に決めればよいか』という内容が増えています。人手不足や物価上昇による賃金上昇圧力もあり、昇給はいまや多くの企業にとって事業計画上の最優先課題です。
政府は『2020年代に全国平均で最低賃金を時給1,500円とする』という目標を掲げており、これが中小企業における賃金上昇の加速要因となっています。
最低賃金とは、国が都道府県ごとに定める時給換算での最低額のことであり、これを下回る賃金で雇用契約を結ぶことは法律違反です。今年の全国平均は過去最大となる66円引き上げの結果、時給1,121円となり、月初から適用されています。
例えば、愛知県では2024年に1,077円から1,140円へと63円引き上げられ、上昇率は約5.85%でした。単純計算では、月給300,000円の従業員であれば317,550円に昇給し、会社としては賃金だけで1人当たり年間210,600円、社会保険料を含めれば月額で20,000円超の負担です。
政府が決定した上昇率である点を踏まえれば、少なくともこれくらいの賃上げが期待されているという意味合いがあり、昇給率として一定の合理性があると考えられます。
実質賃金上昇率
実質賃金上昇率がどのように推移しているかも合理的な昇給の根拠となります。実質賃金とは、労働者が受け取る賃金(名目賃金)から物価変動の影響を差し引いたもので、実際にモノやサービスを購入できる購買力を示す指標です。
受給側の観点では、実質賃金が上がらなければ、物価が上がった分、昨年と同じレベルの生活ができなくなってしまうことになります。そのため、企業は、従業員の生活レベルが年々下がるような事態は避けなければなりません。
実質賃金上昇率は、「(名目賃金上昇率-物価上昇率)/(1+物価上昇率) × 100)」の算式で示されますが、簡便的に統計数値を利用することをお勧めします。
名目賃金上昇率には厚生労働省が毎月発表する「現金給与総額(全産業前年比)」を、物価上昇率には総務省の「消費者物価指数(生鮮除く総合)前年比」を用いるのが身近で理解しやすいでしょう。
例えば、「現金給与総額」が前年比2.5%、「消費者物価指数」が3.3%であれば、賃金の伸びが物価に追いついていない状況です。この場合、従業員の購買力は低下するため、企業としては少なくとも物価上昇率を上回る昇給を努力目標とするのが合理的です。
仮に、「消費者物価指数」を少し上回る上昇率で3.5%にした場合、月給300,000円は310,500円に昇給することになります。
付加価値上昇率
これまでの賃金上昇率は、受給側を納得させるための「世間体」に配慮したものでした。しかし、昇給を実現するためには、それを賄うだけの付加価値(≒粗利益)の上昇が不可欠です。付加価値を上げずに昇給だけを続ければ、利益は減少し、いずれ会社は立ち行かなくなります。
企業体力を維持しながら昇給を継続するには、付加価値の上昇率を基準とするのが合理的です。付加価値額の定義は会社によって異なりますが、一般的には「経常利益+人件費+金融費用+賃借料+租税公課」で算出されます(当レポート№120参照)。
原価と販管費の区分が正確にできていれば、決算書の「売上総利益」を用いることも可能です。売上総利益の上昇率を基準とすれば理解しやすく、また、売上高の増加や原価低減による利益改善は、営業努力や経費削減の成果を反映するため、昇給基準として合理的であり、従業員のモチベーション向上にもつながります。
ただし、同規模のまま売上総利益を上げ続けるには限界があることも考慮しなければなりません。長期的には、規模の経済や範囲の経済を働かせるなど、成長戦略と組み合わせる必要があります。
小規模企業における昇給は「人事評価制度」を整備して活用できるほど経営資源に余裕がありません。適切な人材を採用・確保し続けるためにも、自社の実情に即したより合理的で持続可能な昇給基準を設定することが重要です。
<複製・転写等禁止>