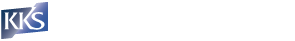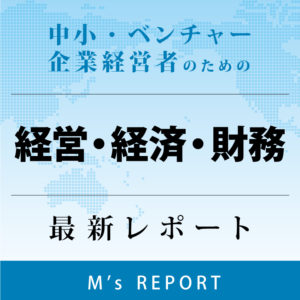第42回 会津若松城 <福島県>

天守台は野面積みで蒲生氏郷時代の数少ない遺構

赤瓦なのがよくわかる。奥から、干飯櫓、南走長屋、鉄門、走長屋
12 会津若松城<福島県>
幕末の戊辰戦争で1カ月にも及ぶ新政府軍の猛攻に耐えた会津若松城の歴史は古く、1384年に蘆名(あしな)直盛が築いた東黒川館(黒川城)が始まりです。
1589年に伊達政宗に攻め滅ぼされましたが、1年余りで蒲生氏郷が入城し、縄張りや城下町を整備して、翌年に望楼型の七重七層の天守閣が完成すると、鶴ヶ城と改名しました。
その後も上杉景勝、加藤嘉明など名立たる名将が入城しましたが、現在の天守閣である楼塔型五層の姿は加藤嘉明の時代に改修され、豪雪地帯ならではの工夫が施された珍しい赤瓦は保科正之が城主の時期に採用されたものです。
明治初期に廃城となり石垣以外の建造物は取り壊されましたが、昭和40年に天守は外観復元され、内部は会津藩の歴史を学べる「若松城天守閣郷土博物館」に、城周辺は鶴ヶ城城址公園となって、当時のままの石垣や縄張り、四季折々の景色を楽しむことができます。
別称:鶴ヶ城
![]() 福島県会津若松市
福島県会津若松市

見どころのひとつである本丸東側の高石垣(扇の勾配)は高さ20mにも及ぶ