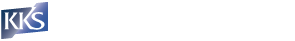№131-R4.5月号 実務上の安全性評価
安全性評価の考え方
職業柄、決算書をベースに財務分析をさせていただく機会があります。経産省のローカルベンチマークや会計事務所提供の決算分析書類などでも「安全性」「収益性」「成長性」といった指標による評価を目にしますが、中でも、特に「安全性」は、会社の存続に関わる重要な指標であり、最も注視すべきデータです。
「安全性」分析には、一般的に、「流動比率」、「当座比率」、「自己資本比率」、「固定比率」、「固定長期適合率」などが使われます。「安全性」は、言い換えれば、経営の「安定性」でもあり、企業が継続的に経営できる状態にあるかをより正確に示すものであることが理想です。
例えば、「流動比率」や「当座比率」が150%超であった場合、その企業の「安全性」は「優良」という評価で問題ないでしょうか? もしかしたら、不良在庫や粉飾による水増しが含まれていたり、特別利益等の一時的な収入で「当座比率」が高くなっているかもしれません。
同様に「自己資本比率」は高く、「固定比率」は低いことが評価を上げますが、資産の老朽化で設備投資が進んでおらず、数年後の安全性は疑わしい場合もあります。「インタレスト・カバレッジ・レシオ」を掲載している分析表に至っては、低金利時代の評価指標としてまったく相応しくありません。
これらを複合的に判断することは、最低限の評価には値しますが、鵜呑みにするのは危険です。
金融機関視点での安全性
決算書の数値から単純計算された「安全性」指標は、総合的な信用度とすれば1~2割程度で、参考程度に過ぎません。なぜなら、本気度が足りないからです。
信用に足る「安全性」を評価するのであれば、「自分だったら、その企業に融資できるか?」つまり、金融機関視点での判断が最も説得力があるのではないでしょうか。
諸説ありますが、実際に金融機関が融資の際にウェイトを置いている指標を3つ紹介します。
最初は、「手元流動性(比率)」です。
算式は「手元流動性(月)=(現預金+短期保有の有価証券等+与信枠)÷月商」で表され、現預金及び短期保有の有価証券等のすぐに換金できる資産(金融機関からすぐに借り入れできる与信枠を加える場合もあります)が平均月商の何倍あるかを示す指標で、企業の短期的な 支払能力を計る尺度とされます。
「手元流動性」が高いほど売上高が急減しても、固定費の支払いや債務の返済余力があり、財務健全性が高いという評価です。中小企業であれば、資金がボトムになる時点(通常は給料日)で、通常時は1.5カ月以上が目安ですが、コロナ禍のような非常事態を想定した場合、3カ月以上が望ましいでしょう。
2つ目は、「債務償還年数」または「EBITDA有利子負債倍率」です。
すぐに返済できない有利子負債が本業の収益の何年分あるかを示す指標で、EBITDA有利子負債倍率は、分母がEBITDA(利息・税金・減価償却費等を控除する前の利益)であるのに対して、債務償還年数は、金融機関によって経常利益、営業利益、当期純利益のいずれを使用するかが異なります。
経常利益であれば、10年以内、製造業のように大規模な設備投資が必要な業種の場合は、20年程度であれば健全な財務状況と判断され、EBITDA有利子負債倍率の場合は支払利息控除前の利益が対象となるため、10倍以内が目安です。この指標で中長期的な安全性が確認できます。
最後は「経常収支(比率)」です。
算式は「経常収入÷経常支出×100%」で算出します。企業の資金繰りの実態を示す指標で、他の分析方法「静的安全性」とは異なり、企業の「動的安全性」を判断するための分析です。特に、粉飾等による利益操作の影響を受け難いと言われています。
経常収支比率の目安は、105%を超えれば優良、95%を切ればかなり資金繰りは厳しく、3期連続で95%、または、1期でも90%を切っていると相当資金繰りは逼迫している状態です。
金融機関は、この3指標を融資判断に採用しています。「安全性」に問題ないはずの企業が融資を受けられない現実は、何を基準に「安全」とするかの認識のズレです。資金調達という観点からも本当の意味での自社の安全性を知っておく必要があります。
<複製・転写等禁止>