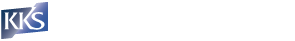№149-R5.11月号 生活経済の縮小構造
平均年収の動向
日常生活において様々な場面で物価上昇が顕著になり、家計の負担が重くなっていると感じるようになりました。スーパーでは若い夫婦がスマホで電卓を使いながら買い物をしていたり、ファミレスなどの外食チェーン店も夜間は人がまばらな光景を目にする機会が多くなった気がします。
名目GDPの推移からも、日本は30年以上経済成長をしていないため、当然ながら給与所得者の平均年収もその間は上がっていません。
毎年国税庁が公表している「民間給与実態調査」によれば、2022年の平均年収は458万円で、30年前1991年の446万6000円と比較してもほとんど上昇していないことがわかります(参考値:2021年は443万円、過去30年で最も高い年は1997年の467万3000円)。
ただ、昨年は前年比で15万円も上昇していますので、この1年間は相当な企業努力があったと見て良いでしょう。 また、年収を平均値でなく中央値で見ると、厚生労働省が3年に1度実施する「国民生活基礎調査」での直近2021年のデータでは440万円と平均値から大きなズレはありません。
しかし、1995年は545万円であることから、中央値は約25年で100万円以上下がっていることになります。上昇率を海外と比較しても、2000年からの20年間は、米国25%、韓国44%に対して、日本はわずか4%です。
可処分所得の減少
平均年収が上がらない要因としては、海外の「成果主義報酬」に対して、「終身雇用」や「年功序列」による報酬体系が中小企業を中心に根付いていることやパート、アルバイトの雇用形態での年収調整などがあげられます。
一方で、給与から徴収される社会保険料は30年で大きく増えている印象です。
社会保険料は、まず、2000年に40 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者に介護保険への加入が義務付けられ、1990年との比較で、健康保険(協会けんぽ)が8.4%から10.0パーセントに、介護保険料が0.60%(2000年)から1.82%、厚生年金保険料が14.3%から18.3%へ保険料率がそれぞれ上昇しています。
2003年4月からは賞与に対しても社会保険料が課さられるようになりました。負担額は会社と折半ではありますが、平均給与が上がらない中での料率の引き上げは可処分所得が減ることになり、家計は厳しくなるばかりです。
さらに、「国民負担率」の観点からも、2000年度の35.6%から2023年度は46.8%へと上がっていますので、給与に占める税金や社会保険料の負担が大きくなっていることがわかります。
これらの統計推移を見る限り、給与が増えなければ、家計として自由に使える金額は今後もジリジリ減り続けることになるでしょう。
物価上昇と実質賃金
日本は長らくデフレの状態が続いていましたので、近年は主に輸入物価の上昇によるコストプッシュ型のインフレに悩まされている状況です。
つまり、景気が上昇して賃金が増え、消費が活性化することでの物価上昇ではなく、海外の景気好調や円安の影響を受けて、輸入物価が上がったことによる止むを得ない物価上昇になっているのです。
デフレ続きで一見物価は長期間停滞していたかのように見えますが、実は消費税率アップという形で物価は上がっています。消費者にとっては、本体価格であろうが消費税であろうが物価が上がったことに変わりはありません。
物価の上昇を考慮した実質賃金で見ると、2000年頃までは物価指数の伸びを名目賃金の伸びが上回り、実質賃金は増加傾向でしたが、現在の実質賃金は1990年の約85%程度と言われます。
平均賃金は変わらなくても、30年前は感覚的にもっと懐に余裕があったのかもしれません。政策や社会情勢から判断しても、現状では中小企業において大幅な賃上げは非常に困難です。
政府は新NISAの導入などで投資による個人資産の増加を促していますが、利回りが良いと言われる海外株式へのインデックス投資でも最低10年スパンでの話ですし、投資資金が捻出できなければスタートラインにも立てません。目先の減税策を見る限り、賃上げの根本的解決にはほど遠い気がします。
<複製・転写等禁止>